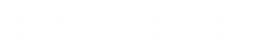トーシンのお役立ち情報
高速道路の豆知識
遠出をするのに欠かせない高速道路ですが、日本にはどの程度高速道路があるか知っていますか?
東伸自動車のある門真市にも、近畿自動車道、第二京阪道路など大きな高速道路が通っています。
高速道路だけでなく、その他の有料道路なども合わせて見て行きたいと思います。
日本の高速道路の歴史
初めて日本に高速道路が開通したのは、1963年兵庫県尼崎市と滋賀県栗東市の尼崎IC-栗東IC間でした。
翌年の東京オリンピックを控え、ここから急速に日本の高速道路網は広がっていくことになります。
1965年に名神高速道路全線が開通し、1966年自動車専用国道の名阪国道が開通します。
1969年東名自動車道が開通され、東京から大阪まで高速道路が繋がりました。
以降、年々全国各地に高速道路が開通していき、現代の日本の高速道路網が完成していくことになります。
日本の高速道路の数
現在、高速道路、自動車専用道路には、外国人の方にもわかりやすいように、道路にナンバリングがされており、E1~E98までとCA・C2・C3・C4の道路があります。
つまり、それだけの高速道路が日本にあるってことですね。思っていたよりもずっと多くて正直ビックリしてます。
高速道路のアレコレ
ICやJCT、NEXCOとか高速道路は専門用語が多くてよくわからん!ってこと多いですよね。普段高速道路に乗らない人は、こういう時どうすればいいの?ってこともあるはずです。一個ずつ簡単に見て行きましょう。出入口と分岐
IC
ICは基本的に、高速道路と一般道の出入口、または料金所のある所のことを言います。
ETCレーンと、昔ながらの係員に料金を支払うタイプと無人精算機で精算するタイプの料金所があり、最近は有人は減ってきています。窓口に人がいないだけで、料金所自体に係員はいるので、トラブルの際もご心配なく。
スマートIC
近年、一部で導入され始めているICです。
スマートICはETC車載器を搭載している自動車のみが利用出来るICになっています。
係員は常駐しておらず、設備も簡易で済む為に設置コストが抑えられる利点があります。
ICによっては利用可能時間や、大型車は利用出来ないなどの条件がある為、注意が必要な他、よく勘違いしがちなのが、ETC専用の為にそのまま通過しようとする人が多いですが、ゲート前にて一旦停止をして設備と通信を行う必要があります。
JCT
JCTは複数の高速道路や出入口を繋ぐ分岐点のことを指します。
中には複数の道路が複雑に入り組んで、通り際にパッと案内標識を一瞥しただでは理解不能なJCTも存在する為、そういったJCTを利用する場合は事前に下調べをしておくことをおすすめします。
日本一難解と言われる垂水JCTは道路上と案内標識で色分けを実施し、比較的わかりやすい対策を取っていますが、それでも誤進入をする人は後を絶ちません。
表示関係
渋滞情報
高速道路の渋滞情報は、高速道路上の看板や交通情報ラジオで知ることが出来ます。
高速道路上には、通過する自動車の速度や種類を判別している計測器が設置されていて、時速40km以下での通行が続くようであれば渋滞といった判定がなされているようです。
また、高速道路を巡回しているパトロールカーの職員によって、目視でもリアルタイムで情報が送られています。
道路情報を表示する電工掲示板では、渋滞時は黄色のランプが点灯し、通行止め時は赤色のランプが点灯するようになっています。
R標識
黄色いひし形のR=数字の看板を見たことありませんか?あればカーブの半径を表している看板になります。
高速道路は、道路の設計速度によって、やむおえない場合以外はこれ以上のRでカーブを作りなさいと言った基準があります。
設計速度120kmでR=710以上、100kmでR=460以上、80kmでR=280以上に設定されています。
Rが小さくなればなるほどカーブがキツくなっていきます。
中国自動車道には日本一Rのキツイ、R=200のカーブがありますが、道路自体が古く急カーブが多かったり、道幅が狭かったりと、基本的にこの辺りの区間は60kmや80km制限になっています。
R=200がどれくらいなのか?と思う人で、ピンと来る人にはわかりやすいのは、鈴鹿サーキットのヘアピン立ち上がりからスプーン進入までが200Rです。
勾配標識
黄色いひし形で、斜め矢印に数字%の看板がありますよね。これは、上り又は下りの勾配の%を表している標識です。上り方向10%なら、100mで10m上りますよってことになります。
上り勾配では速度が落ちやすく渋滞が発生しやすく、下り勾配では速度が出て事故が発生しやすい為に表示されたりします。
急勾配の道路に設置されている為、勾配標識を見かけたら周りの状況を見ながら注意して運転をする必要があります。
キロポスト
高速道路の路肩などに数字の書かれた小さな看板があります。これはキロポストと言って、その高速道路の起点からの距離を示しています。
なんの為に使用するの?と言いますと、事故や落下物などがあって通報したりする時に、〇〇道路の何km地点と的確に報告を行ったりする場合に利用します。
警察や高速道路のパトロールが正確に素早く現場に駆け付ける為に、とても役に立つ標識となっています。
設備関連
トンネル内のファン
長いトンネル内などで、天井から大きなファンがぶら下がっているのを見たことありませんか?
あれは、ジェットファンと言う物で、トンネル内に新鮮な空気を取り入れたり、排気ガスやホコリなどを排出して、トンネル内の空気を綺麗に保ったり視界を確保する為に設置されています。
このファンは、フルパワーで稼働した場合に発生させる風は、風速30mにも及びます。
非常電話
高速道路では、1km置きに非常電話が設置されています。
緊急の際に利用することになるのですが、受話器を取った瞬間から管制センターに繋がり、発進元の非常電話の位置が特定される為、素早い対応をすることが可能になります。
なんらかの原因で携帯電話が通じない場合などにも使える為に、非常電話は重要な設備となります。
声を発するのが難しい場合でも、「事故」「救急」「火災」「故障」の押しボタンによって大まかな状況を伝えることが出来るようになっています。
退避所、非常駐車帯
高速道路上で、故障や事故などが発生した時の為に、退避所や非常駐車帯が設置されています。
高架部分では500m置きに、トンネルでは750m置きに設置されています。
非常時に停止する為の場所になるので、携帯電話の通話の為の停車や、仮眠を取る為に停車した場合などは交通違反で検挙される場合もあります。

こんな時はどうすれば?
ETCレーンのバーが開かない
ETCカードや車載器などのトラブルによって、ゲートでバーが開かなかった場合の対処法ですが、まず、事故などを回避する為に、ハザードランプ等で後続車へ合図を送ります。
バーの前で停止し、インターフォン等で係員の指示に従いましょう。
バイクなどの場合は、安全な場所へ車両ごと退避を指示される場合もあるので、従いましょう。
やむおえず突破してしまった場合は、停車すると危険になりますので、入口ゲートの場合は出口料金所の有人レーンで事情を説明しましょう。出口ゲートの場合は、管轄の各高速道路会社に連絡をして、支払いなどの指示に従いましょう。
故障が発生した場合
高速道路を走行中、自動車になんらかのトラブルが発生した場合は、まず自身と周囲の安全を確保することが最優先になります。
やむおえず本線上などで停止する必要がある場合は、路肩などになるべく寄せて停止し、停止板や発煙筒によって後続車に停止車両の存在を知らせます。
乗員は全員、自動車より後方のガードレール外に退避します。パンクや故障などの場合においても、自身で対処しようとせずに、警察や道路緊急通報ダイヤルへの通報を行い、指示に従います。
二次災害の原因となりますので、自身で対処してはいけません。
あおり運転に遭遇した場合
昨今、大きな社会問題となっているあおり運転ですが、高速道路を走行中にあおり運転の被害に会ってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
まず、なるべく左車線へ寄り、相手に進路を譲るようにします。追い越し車線では速度の速い自動車が多い為、事故など二次災害の可能性が高まります。
進路を譲っても尚、相手が煽り運転を止めない場合は、最寄のSAなどへ退避したり、出口から降りるようにしましょう。
万が一本線上で停止させられてしまった場合でも、絶対に車外へ降りてはいけません。ハザードランプなどで後方へ知らせた上で、ドアを全てロックして警察へ通報しましょう。
急ブレーキなどで報復などをしようとしたりせずに、あおり運転を受けた場合は速やかに警察に通報することが重要です。
また、あおり運転に遭遇しない為の運転を日頃から心がけるようにしましょう。
無理な進路変更などをしない、後続から速度の速い自動車が来た場合は、速やかに進路を譲るようにする、周りの交通の流れを阻害する運転をしないなどが大事になります。
トンネル内で火災に遭遇した場合
トンネル内などで、火災に遭遇して完全に流れが停止してしまっている場合は、速やかに非常口より避難しましょう。
避難の際は、自動車はキーを付けたままにし、ドアロックをしないで置いていきます。
これは、緊急車両などが到着した際に、緊急車両の交通を阻害しない為です。
地震が発生した場合
高速道路を走行中に地震が発生した場合や、緊急地震速報などを受信した場合の対処ですが、まず急減速や急停車などをしてはいけません。
ハザードランプを点灯させ、ゆっくりと減速して左側の路肩へ停車します。
ラジオや高速道路情報の指示に従いましょう。津波などの可能性がある場合は、指示に従い避難をします。
自動車を離れる際は、火災の場合と同様に自動車のキーを付けたまま、ロックせずに離れるようにしましょう。
雑学
NEXCO
NEXCOとは、旧高速道路公団の民営化によって誕生した民間の高速道路会社になります。東日本、中日本、西日本の3社があり、これらの総称となります。
主に、高速道路の管理や運営などを行っている会社となります。
黄色い自動車
よく高速道路上を黄色い自動車が走っていることがあります。あれは高速道路パトロールカーと呼ばれ、高速道路の安全確保や保全などを行っています。
落下物を回収したり、故障車などが発生した場合に現場に駆け付けたりします。
管理運営はNEXCOが行っています。
高速道路の舗装
高速道路の舗装は、高機能舗装と呼ばれ、高い排水性と吸音性を持った舗装がされています。
高速走行時は、特にハイドロプレーニング現象が発生しやすくなる為、排水性のよい舗装が重要となります。
ETC問題
近年、ETC2.0など新型の車載器が登場していますが。現行のETC車載器が2022年以降に使用出来なくなる機械があります。
これは、電波法の改正によって2007年以前に認証を受けた機械の電波が違法となる為、車載器が使用できなくなると言った物です。
更には、2030年に今度はセキュリティに関する規格の変更が予定されている為、更に多くの車載器が使用出来なくなる可能性があります。

高速道路の取り締まり
高速道路における取り締まりは、各都道府県警に設置された「高速道路交通警察隊」によって行われています。
同隊は、高速道路上で発生した事件・事故全ての捜査権を持ちます。
移動式オービスによる取り締まり
通常の常設型オービスによる取り締まりはまぁ置いておいて、神出鬼没恐怖の移動式オービスの取り締まりは高速道路でも行われています。
基本的に、赤切符になる速度からオービスは作動するように設定されていますので(あくまで基本です、例外もアリ)、高速道路では40kmオーバーから取り締まりを受けることが多くなります。
そもそも、1kmでもオーバーした所からスピード違反は成立しますので、ご注意下さい。
覆面パトカーによる取り締まり
高速道路上でもっとも警戒すべきは覆面パトカーによる取り締まりでしょう。
大阪の高速道路で言いますと、クラウン・マークX・スカイライン・レガシィB4の覆面パトカーが存在しています。
基本的に、制服とヘルメット着用の2名乗車で背筋ピーン!なので、注意していれば非常にわかりやすいのですが。
追い越し車線が妙にガラガラなのに、走行車線に大名行列が出来ている場合なども、間や先頭などに覆面パトカーが潜んでいることがあります。
車検切れ車両の取り締まり
一般道でも行われていますが、ナンバー読み取り機を使用した車検切れ自動車の摘発が、高速道路上でも行われています。
実際に、2019年に和歌山県内の阪和自動車道にて西日本で初めて実施され、大阪や門真市周辺ではまだ実施はされていませんが、今後も各地域で取り締まりが実施されることが予想されます。
高速道路を安全に運行する為にも、車検や整備などは適切に行う必要があります。
大阪環状線
阪神高速道路1号環状線と呼ばれ、大阪市内をぐるりと一周するループ構造の高速道路です。
10分ちょっと位で1周出来る為、降り口等を間違えた場合でも、慌てずのんびり流していればすぐに戻ってこれる他、ひたすら無心で流していたい場合なんかに、延々とグルグル回って時間を潰せる路線となっています。
平成初期には「環状族」と呼ばれる暴走集団によって、夜な夜なサーキットもどきに使用されることもあり、Hシステム(レーダー式オービス)は阪神高速の頭文字を取った物でこの頃の名残となっています。
一般車を巻き込んだ死亡事故なども多発し、連日連夜警察による検問や封鎖なども行われ、Hシステムの普及や、時代の流れと共に、現代では絶滅したかに思われていましたが、2020年コロナ騒動で、首都高ルーレット族が検挙されたニュースが記憶に新しい所ですが。
実は、大阪府に緊急事態宣言が発令され、深夜帯になると、高速道路もほぼ通行する自動車が居なくなった為に、どこからともなく湧き出てきた環状族のパラダイス状態になっていました。この時代に一体何をやってるんだか。関西の高速道路渋滞ポイント
関西の高速道路で、よく渋滞するポイントはどこでしょうか?
事前に知っていれば、迂回などで回避して時間の有効活用になるかも知れませんね。
名神高速道路、大津IC付近
京都方面から京都東IC~大津IC付近での渋滞が発生しやすくなっています。
京都東ICからの合流と、すぐにトンネルがあることによって流れが悪くなりやすい為、渋滞が発生しやすいポイントになっているようです。
一般道でも距離的にはほとんど変わらないので、ここが混んでいる場合は渋滞を回避しようと安易に一般道に降りてしまうと、県境の国道1号線がもっと渋滞していてド嵌りすることがあるので、大人しく高速道路を走りましょう。
草津JCT付近の渋滞と合わせて、酷い時は大山崎まで渋滞が伸びることがありすが、大体の原因になっている戦犯はここになります。
阪神高速、阿波座出口付近
阪神高速3号神戸線と16号大阪港線の合流部分に阿波座出口と1号環状線への合流があり自動車が右へ左への大騒ぎで渋滞の発生ポイントになっています。
車線が増やされたり、新JCTが設置されたりで解消には努めていますが、そもそも阿波座出口の信号待ちの自動車が本線まで溢れて渋滞してるのであんまり関係ないじゃないかな!
第二神明道路、名谷IC
神戸淡路鳴門道へ繋がる為、垂水JCT付近の混雑のツケを食らって渋滞するポイント。GWやお盆など、長期休暇になると恐怖の渋滞が発生する名物地点。
大体の原因は明石海峡大橋と垂水JCTのせいであるが、宝塚渋滞と合わせて神戸近辺のこの辺りは非常にカオスな様相を呈することになります。
中国自動車道、宝塚トンネル付近
ただでさえ渋滞しやすいトンネルに加えて、阪神高速11号池田線、7号北神戸線、舞鶴若狭自動車道、山陽自動車道などの合流地点となるJCTが周辺に集中する為、もうお手上げ状態の渋滞ポイントと化します。
新名神高槻JCTの開通によって分散が期待されていますが、果たして。
阪和自動車道、泉佐野JCT以南
暖かい時期の連休やお盆休みになると、白浜を目指す人達で渋滞が発生するポイントです。
有田IC以南が1車線になる為、酷い時はここから延々と渋滞が発生して泉佐野位まで伸びています。
一般道で南下しようとするともっと渋滞しているので、もうみんな白浜行くの諦めたほうがいいんじゃないの?と個人的には毎年思っています。
名阪国道、Ωコーナー付近
天理側から名阪国道に入ってすぐにΩコーナーと呼ばれるとんでもない形のカーブがあり、勾配もキツイ為に、速度の出ない大型トラックやら、事故やらで連休にはアッと言う間に渋滞が形成されます。
名阪国道で済む訳がなく、渋滞は西名阪自動車道藤井寺辺りから延々と続くことも。
なにより名阪国道は国道の為無料なので、亀山方面向けの利用自動車が多く渋滞しやすくなっています。
高速道路の老朽化
日本の主要高速道路の多くは、初期に開通した道路が多く、4割以上が開通から30年以上が経過しています。
その為、高速道路の老朽化が進み、維持の為に1年中を通して、様々な区間で大規模修繕工事などが行われています。
工事中は、利用者の私たちは不便に感じることが多くなりますが、安全で安心な高速道路の利用の為には必要なことになってきます。
今後20年で、耐用年数50年を超えるトンネルや橋などが7割を超えると言われており、今後この問題をどうしていくかが、日本の安全な交通網において大きな課題となっています。

SAとPAと道の駅
高速道路には、SA(サービスエリア)とPA(パーキングエリア)がありますが、この違いはご存じですか?
一般的には、規模が比較的大きな物がSA,小規模な物をPAと呼んでいたようですが、最近では大型のPAの登場などによって、呼び方の区別にあまり意味は無くなっているようです。
SAが概ね50kmおきに設置されるのに対して、PAは概ね15kmおきに設置されますが、例外もあり、必ずしもこのような感覚で設置されている訳ではありません。
中には150kmほど無い区間もありますので、色々な意味で注意が必要になります。
自動販売機や売店、飲食店などが設置され、長距離運転中の休憩を行うことが出来る施設になります。
規模などによって施設も様々で、観光地化しているような大規模な所もあれば、数台の駐車スペースにトイレと自動販売機のみ、といった簡易な物まで様々です。
無料の自動車専用道路などでは、道路外に道の駅などが隣接して、SA等の役割を果たしている場合が多くあります。
近畿地方で人気のSA等をちょっと見てみましょう。
桂川PA
名神高速道路の京都府内にあるPAです。PAとしては、比較的大型の物になりますが、そもそも京都にはSAは無かったりするのですが。
吹田SAと大津SAの間にあり、位置関係的に休憩する人も多く、比較的いつも混雑傾向にあるPAになります。
大津SA
琵琶湖を一望出来る位置にあるSAです。
2013年に下り側施設がリニューアルされ、かなり綺麗になりました。
上り側には恋人の聖地が設置されいます。琵琶湖花火大会を眺めることも出来る為、花火大会当日は見物目的の人が結構いたりします。
以前は上り側と下り側を連絡橋によって徒歩で行き来出来ましたが、現在は出来ないようになっています。
琵琶湖らしく珍しい物になると、ブラックバスのフライの丼を提供しています。
岸和田SA
阪和道岸和田料金所近くにあるSAです。
比較的単調な道が続いてSA間の感覚が広い近畿道、阪和道において絶妙に寄りたくなる位置にあります。
タイガースショップやなんちゃって日本庭園があり、規模もそこそこ大きな為、比較的ゆっくりと過ごせるSAになっています。
堺近辺や和歌山のお土産を比較的多く置いていますが、和歌山のお土産については後述の紀ノ川SAでいいのでは?と思うのは突っ込んではいけない所なんでしょうか。
上り側では有名なみかんパンを販売しています。
紀ノ川SA
阪和道を和歌山に入って間もなく出てくるSAです。
下りの白浜方面へは、本SAが最終の給油ポイントになるので注意が必要になります。
下り側ではベーカリーが設置され、焼き立てパンを購入することが出来ます、コーヒーランドがおすすめですが、売り切れていることも多いです。あとは半熟卵入りのカレーパンも美味しいですよ。
泉大津PA
阪神高速道路にあるPAです。関西国際空港からの最寄PAになります。
こちらのPAも上り側と下り側が連絡橋で繋がっている為、徒歩での行き来が可能です。
上り側には24時間利用可能な展望ラウンジがあり、工業地帯と大阪湾の夜景を楽しむことが出来ます。また、PAでは日本初のカプセルホテルが併設されています。
小型車は比較的余裕がありますが、大型車Pは安定して混雑している傾向にあります。
淡路島SA
神戸鳴門自動車道を本州側から淡路島に入ってすぐの所にあるSAです。
上り側下り側が自動車で自由に行き来可能で、同じく行き来可能な淡路島ハイウェイオアシスが併設されています。
規模としてはかなり大きな物になり、淡路島SA目当てに訪れる人も多くいます。
上り側には恋人の聖地が設置されており、下り側には観覧車が設置されています。
上下側とハイウェイオアシスを合わせると、半日位は余裕で潰せる位のボリュームがある為、迂闊に休憩に寄ると思わぬ時間を取られることになることは確実です。
多賀SA
名神高速道路、彦根IC近くにあるのが多賀SAです。
近江牛を使用したメニューが豊富で、上り側にはドッグランが、下り側にはホテルが併設されており、ホテルは大浴場のみの利用も可能となっています。
名古屋と大阪のちょうど中間地点位にある為、長距離の休憩に程よい施設となっています。
こちらのSAも上り側と下り側の行き来が出来るようになっています。
道の駅 針テラス
名阪国道最大の休憩スポット。天理側より名阪国道に入って15kmほどの地点にあります。
年中多くの人で賑わい、バイク用品店のクシタニが運営するカフェが入っており、ツーリングの起点や休憩しやすい位置ある為、特にバイク乗りの人達が集まる傾向にあります。
温泉施設や、20年夏頃にはカプセルホテルもオープン予定で、名阪国道利用者の憩いの場となっています。
まとめ
今回は、日本の高速道路について触れました。
遠出をする際などには利用する機会も多くなるのが高速道路なので、適切に利用して安心したカーライフを送りたいですね。

- 自動車のブレーキとは?
- 自動車でよく耳にするエンジンオイルとは?
- タイヤのサイズの見方から細かな事まで一気に解説
- 知って得するお手軽ボディコーティング
- 自動車のチューニング入門(ライトチューン編)
- 車検の有効期間や予約方法について
- 車検の時の4ナンバーとか3ナンバーって?
- 免許と更新と門真運転試験場
- 免許証の点数や交通違反の取り締まりアレコレ
- 運転のコツ
- 車のバッテリーの繋ぎ方や基本と対策
- 軽自動車ってなに?
- 意外と知らないカーナビの違い
- 認証工場と指定工場の違いと車検
- よくわからない、自動車のハイブリットと燃費のこと
- 高速道路の豆知識
- 門真の整備士が語る輸入車と輸出
- 門真市周辺の車検費用の相場
- 門真の整備士が語る、車検に落ちる原因と対策
- 門真の工場に来て思った自動車整備の工具
- 整備士が語るモータースポーツ
- 車検が切れてしまった場合の車検
- 自動車技術の高度化と車検
- 12か月点検と6か月点検の内容と違い
- 車検以外の点検の必要性
- 自動車のリコールとは?
- 地域別の車検や自動車の違い
- 門真の整備士が語る「新時代のカーライフ」
- 門真の整備士が語る「車の構造変更」
お問い合わせ
不明な点やご質問など、こちらよりお気軽にお問い合わせいただけます。